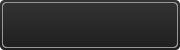- ホーム
- ブログ
ブログ

46「春の始動へ向けて整えています」
2025/02/15
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
立春を過ぎてもなお
寒さが厳しい日が続きますが
確実に春へと季節が進んでいるのを感じます。
朝焼けの美しい時間が
日増しに早くなり
スイスにいる次女と話しているうちに
すっかり明るくなります。
そして夕方。
夕闇の迫る頃が
徐々に遅くなって
夕食の準備を慌ててしないと
夜の時間が短くなってしまいます。
夕食を食べながらドイツの長女と
気楽なおしゃべりを。
2月も後半になると
そろそろ私も仕込みを終えて
動き出さなければなりません。
現実逃避生活もそろそろ終わり。
頭の中で鳴っている音楽を
外に向けて
発信していかなければ・・・
小さなコンサートから
大きなコンサートまで
また皆さんにお会いできることを
楽しみにしています。
45「音楽家と言葉」
2025/02/14
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
音楽家は音で曲を表現するので
どちらかというと言葉をおざなりにしがちです。
「表現するのが難しいけれど・・・」
「言葉にできないから、こんな感じ・・・」
「なんとなく、こんな風に・・・」
私もピアニストに細かいニュアンスを伝えるときに
曖昧な言葉で逃げてしまう時があります。
また「とにかく弾いてみましょう・・・」と
時間を気にして次のステップへ行ってしまう時もあります。
でも、
近頃は、なるべく少しでも何かが伝わるように
言葉をかえてみたり
例を挙げてみたり
反対方向から伝えてみたり、と
意識的に言葉を使うようにしています。
急がば回れ
じっくり伝えた方が
相手が「あぁ、なるほど」と
充分に理解することができたり
納得することができたり
腑に落ちるということができているように感じます。
伝えるときに
自分の思っているぴったりの言葉を
選び取ることの大切さ。
それは日本語だからできることかもしれません。
日本語は素晴らしい言語だと思います。
何かを説明するにも
多様な言葉が存在します。
英語やドイツ語は
ひとつの事柄に対しての単語の数は
そう多くありません。
どちらかといえば
直接的で
簡潔で
ひとつの言葉が
どのシチュエーションでも
使いまわすことができます。
(私はそれで助けられています💦)
英語もドイツ語も
ストレートに伝えたいことを言ったり
わからないことを質問することができるからです。
・・ラクです・・
でも、日本語にある様々な
ニュアンス
言い回し
陰に隠れた真意(を、ぼかすテクニック)
ひっかけ問題的な言葉のあや・・・
などを使い分けることの
楽しさや難しさは
母国語だからできることです。
そのひとさじの言葉の塩梅(あんばいって日本語らしいなぁ)を
意識的に使いこなすことができるのなら
音楽を奏でることも
もっともっと、ずっと奥深いものになっていくのではないかと思います。
子どもの生徒さんには
「読み聞かせをしてもらったり、自分で本を読んでみましょう」と
声掛けをします。
大人の生徒さんにも
「時間がないことは重々承知していますが、本を読むクセをつけましょう」と
お勧めしています。
私自身も、様々なジャンルの本を
楽しく(時間がなくて苦しく・・・)読んでいます。
週末に、本屋さんに行って本を選んでみませんか?
44「習い事に思うこと:娘たちの場合」
2025/02/13
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
習い事の場所は、サードプレイスにもなる
我が家の場合をお話ししましょう。
私は自分の子育てに自信が無かったので
周りの人を巻き込んでいこうと決めていました。
夫はもちろんのこと
実父、サポートシステム、ママ友
そして、習い事の場所も大切でした。
長女は英語と乗馬とヨットの習い事を経験しています。
どれも自分で選びました。
楽しく学び、それなりに身についているようです。
小学生の時にスイミングスクールに短期講習だけ何回か通い
4泳法を取得したのは、運動神経が良かったからかもしれません。
次女は幼稚園の頃からスイミングスクールに通い
小学校2年生から選手コース。
合宿や大会の日程をこなしながら、乗馬に通い
ヴァイオリンを細々と続けていました。
彼女たちはそれぞれの場所で
それぞれの指導者から
それぞれの友達とともに学び
それぞれに確かな
自分の居場所がありました。
どこかの場所でトラブルがあっても
他の場所に逃げ道があり
たとえ何かにつまずいたとしても
どこかの場所が癒してくれるように
「世の中にはいろんな人がいる」ということを
幼いころから知る機会が多かったように思います。
そのため
人を見る目はかなりシビア・・・
自分に危害を与えそうな人を敏感に感じ取って
距離をおくことができます。
だからといって
安心できる人にどっぷり寄りかかることもありません。
それって、とても大切なことなんですよね。
私が彼女たちに伝えたことは、
「世の中にはいろんな人がいるよ」
「すぐにジャッジしないで少し考えよう」
「先生、というのは腐っても先生。
なぜなら、先生と言われるくらい
専門知識を勉強した人だから」
合わない習い事、先生というのは苦痛なものです。
でも、すぐにあきらめてしまわないで
少し様子を見ることも大切です。
ほんの少しの辛抱で、得ることは2倍にも3倍にもなります。
でも、それ以上の我慢は不要。
見極めるところは親の出番だと思います。
冷静に子どもを見る目。
なかなかできませんが
そういう訓練をすることも
大切なことかもしれませんね。
子育てって自分育て。
色々学んでいます(現在進行形💦)
43「ヴァイオリンを習うことはサードプレイスを得ることでもある」
2025/02/12
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
先日読んだ本の中に
【家庭は牢獄にもなりうる】という一文を見て
ドキリとしました。
親と子どもだけの家庭。
忙しくて時間に追われる親。
実家が遠くて助けを求められない。
地域なんてよく知らない。
子どもが少し気難しいのでお友だちと一緒に遊べない。
出かけると騒ぐ子どもを連れて出かけられない・・・
孤立した親子だけの家庭では
子どもは親の価値観しか知ることができない。
世の中には様々な意見があり
対立と協調を繰り返しながら
自分を知り
自分を表現していく過程を
親だけの意見で育っていくことの危うさ。
そこに習い事という選択肢を持ってほしいと思います。
家庭でもない、集団でカリキュラムをこなす場所でもない
専門家の先生のいる場所。
ひとつのことに没頭できる時間が
1時間でもあれば
ホッとひと時息を抜くことができます。
家に帰っても、その習い事を復習する時間があれば
凝り固まった考えをほぐすことができます。
没頭することによって
逆に他の考えを受け入れる、
気づきになることもあります。
習い事の場所が、安全安心な場所であれば
子どもにとって、ひとつ居場所が増え
考えの幅が広がり
行動に自信がもてるということです。
私のレッスンは、どちらかと言えば厳しくて
最初のうちは決めごとがたくさんあって
面倒だと思うことがあるかもしれません。
でも、その期間を通り過ぎた時に
気がつくことがあります。
「この先生に何を言っても
この場所は安全だから外に漏れることはないんだ」
「この場所に来て自分の考えを言っても
否定されない、意見を言う時間がある」
そう思ってもらえる場所です。
習い事は自分の能力を高めることだけではありません。
ひたすら自分の身体を動かす
動物と協同する
自然のなかに溶け込む
そんな習い事も良いでしょう。
その場所が
自分の逃げ場所になるのであれば
習い事も
大きな役割を担うことになります。
サードプレイス
子どもだけではない
大人にも必要なことでもあります。
そんな目で
「ヴァイオリンを習う」ということを
考えてみてはいかがでしょうか?
42「ビールもヴァイオリンも練習」
2025/02/11
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
ドイツに留学していたころの話。
クラスコンサートの打ち上げで
炭酸入りミネラルウォーターを飲んでいた私に
ドイツ人のヴァイオリンの師匠が
「いいか、カオリ。
ビールを飲むのは練習だ。
練習すれば
呑み方を覚えるんだ。
たくさん飲んで
色々呑んで
好きなビールを探すんだ!」
あまりビールには興味のなかった私ですが
その言葉はなぜか
とても素直に頭にスッとはいってきました。
ビールを飲むのも練習かぁ。
各地の様々なビールを飲むことを覚え
造り酒屋さんの美味しいビールを飲み
かなりたくさん、楽しく飲めるようになりました。
ドイツのビールはそれほど冷えていませんが
樽から直接注がれたビールは新鮮で
ゴクゴクと飲めます。
(大体1杯が200㎖くらい)
ミネラルウォーターより安い値段なので
カラリと乾燥した空気に
ビールはとてもおいしく感じます。
5月からの季節は
昼間に
外のテーブルで立ち飲みするのが最高。
レッスン帰りに友人と
一杯飲んで帰る、なんてことも。
よく考えたら
ヴァイオリンの練習も同じだな・・と
後になって思いました。
たくさん練習して
いろいろ試して
自分の音楽をみつけるんだ!!
さすが師匠。
そういうことなんだ、と納得。
今はたくさん飲めなくなった
缶ビールを片手に
「師匠はどうしているのかな」と
ドイツに思いをはせる夜。
関連エントリー
-
 273「5冊のノートを駆使しています」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。ノートの話・つづき。私はノートを複数使っていま
273「5冊のノートを駆使しています」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。ノートの話・つづき。私はノートを複数使っていま
-
 274「秋の気配を感じて」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる
274「秋の気配を感じて」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる
-
 275「ほんの少しの積み重ね」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある
275「ほんの少しの積み重ね」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある
-
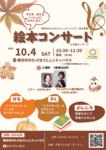 276「心に届く演奏を」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。
276「心に届く演奏を」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。
-
 277「絵本コンサート・終了と反省①」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子
277「絵本コンサート・終了と反省①」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子