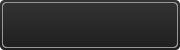- ホーム
- ブログ
ブログ

167「練習にエアコンつける?」
2025/06/16
166「続・本を読む」
2025/06/15
「わたしの渡世日記 上下」高峰秀子(文春文庫)
とにかく読み応えのあるエッセイだった。
毎週1回分、1年にわたるエッセイ。
それも1回分が原稿用紙10枚以上(4000字)なのだからものすごいことだと思う。
それを物書きではない女優が書き上げるのだから「えらいこっちゃ」である。
戦前から戦後までの間、高峰秀子という子役から女優へと進む道にある、様々な人間関係と出来事と世界情勢と、混とんとした彼女の心が浮き彫りになる。
子役としての仕事のため学校へも行けず、毎日毎日撮影所の往復。
『子供にとっての一番の喜びは「学問」以前に「子供同士が友だちを作りあう」ことであり、「生まれて初めての小学校における「集団生活」の経験だと、それをついに持つことの出来なかった私は、自信を持っていうことができる。』
『せめて子供のときくらいは、自然な子供の世界で、子供らしく遊ばせ、子供同士の会話を持たせてやってほしいと私は願う。』
『子供には、感受性はあっても、大人の鈍感さはない』
学校へ行きたいという願いも、人気絶頂の彼女にはその選択が現れては消え、結局学校へ通うことができなかった。
だが、彼女には常に【本物の「師」】が常に周りにいた。
監督や俳優、職人から財界人、文豪や芸術家などありとあらゆる人。人間関係ほどすべての勉強に勝るものはないかもしれない。
そして彼女自身も、基礎的な勉強はやはり大切なことだと彼女自身も悟っていたはずだ。
「無知な人間ほど無謀である。」(文中より)
「ほかに喜んでくれる人がいなかったから、自分で喜ぶよりしようがなかった。」(文中より)
「可哀そうに、君は人間として、言葉は悪いが片輪なんだね」と結婚した松山善三に言われてホッとする彼女。
165「本を読む」
2025/06/14
「巴里ひとりある記」高峰秀子(河出文庫)
1951年6月から翌年1月までの間、そのうちの6ヶ月近くを過ごしたパリでの生活についてを綴る。
本人は辛いこともあってけれど、楽しいことを綴ることが好き、という著者の心もあって内容はどこまでも明るい。
そこかしこに
「それは大変なことだよね」とか
「その状況の裏側は寂しいかも」
という私の余計な思いが漏れ出てしまう。
海外に一人で暮らすというのは、思っている以上に寂しくて厳しい。
それがその生活に必死だったり、なにか目標があったりすれば何とかやり過ごすことができるが、
後で思えばホロリとすることが多い。
50年代当時のヨーロッパは日本から遠かった。
南回りで延々と乗り継ぎをしながらパリにたどり着く様子はそれだけでため息が出る。
パリに到着しても「お金がない」ので洋服はいつも同じもの。
そのうち仕立て屋さんでコートを注文して採寸する様子はさすがに女優。
5歳から子役として仕事をしながら、学校へも行けず撮影場所がすべての勉強場所だった彼女が、
「これではダメだ」
と一念発起してパリへ行く様は、意地悪な見方をすれば、
「そら、女優さんの一興だから、いろんな支援者がいるじゃない。大したことない。お嬢さんの気まぐれ」
と思うが、読み進めていくうちに
「そうではないらしい」と謎が深まる。
その答えは彼女がその後、50歳間近に書いた「わたしの渡世日記」で明らかになるのだが。
とにかくこの1冊から、私にパリの景色がありありと想像できた。
それは、意外なことに彼女の描写が的確だったからに違いない。
そしてパリは、今も昔も基本的なところは変わらないのだ、と歴史の大きさを感じざる得ない。
所々に描かれたスケッチがおしゃれで小粋。
彼女はやっぱり本物の女優で才能があるんだな、と思い知らされる。
164「練習するハードルを下げる」
2025/06/13
163「らせんをグルグル」
2025/06/12
- 仕方ない、とあきらめて身をひそめる
- ひとつだけでも用事を済ませる
- 身体を動かす(私の場合は太陽礼拝をひたすらする)
-
 275「ほんの少しの積み重ね」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある
275「ほんの少しの積み重ね」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある
-
 276「心に届く演奏を」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。
276「心に届く演奏を」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。
-
 277「絵本コンサート・終了と反省①」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子
277「絵本コンサート・終了と反省①」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子
-
 278「絵本コンサート終了と反省②」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。コンサートで反省文を2記事も書くなんて・・・ち
278「絵本コンサート終了と反省②」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。コンサートで反省文を2記事も書くなんて・・・ち
-
 279「中秋の名月と練習」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。涼しくなってきたので夏に使用したものを片づけま
279「中秋の名月と練習」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。涼しくなってきたので夏に使用したものを片づけま