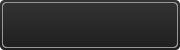- ホーム
- ブログ
ブログ

10「私の習い事はじめ」
2025/01/10
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
今日は少し番外編のようなお話を。
みなさんは習い事を始めるきっかけというのは何でしたか?
「テレビ番組を見て」
「近所のお姉さん(お兄さん)の影響」
「親の勧め」
「気がつかないうちに」等々
私自身は、姉の弾いていたピアノが楽しそうだったので
自分も弾きたいといったけれど、
何だか知らないうちにヴァイオリンを持たされていた…
言い出したのは4歳頃でしたから
それまで習い事の経験はありません。
ただひたすら外で遊んでいました。
外遊びに疲れて帰ってくると
姉がピアノを練習していて
こっそりピアノの下に潜り込んで
寝そべって聞いていました。
ピアノの音が降ってきて
自分を包む感覚が心地よく
低音部を奏でると
心臓部分が揺れる感じが
ワクワクしました。
上手だとか下手だとか
何にもわからなかったけれど
毎日同じ曲を聞くのは嫌じゃなかったです。
「お姉ちゃんの邪魔をしないでこっちにいらっしゃい」と
母に言われても、寝たふりをして動きませんでした。
(姉はイヤだったかもしれないけれど💦)
父が頑張って手に入れたマイホーム。
エレクトーンからアップライトピアノに代わり
そのうちピアノの先生からの斡旋で手に入れた
ヤマハのグランドピアノ。
どういった経緯でそのピアノが我が家に来たのか
わからなかったけれど
その時の父の得意そうな顔は覚えています。
高度経済成長期。
朝から晩まで働いていた父の顔を見れるのは
週末だけだったあの頃。
私たち姉妹と父をつなぐ絆が習い事だったのは確かなことです。
懐かしい思い出です。
今は両親ともに亡くなり
姉は視覚障碍者となってピアノが弾けなくなりました。
でも、あの頃の光景は
鮮やかに私の心に残っていて
キラキラと輝く大切な宝物です。
9「メトロノームは友達?」
2025/01/09
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
メトロノームって知っていますか?
音楽家であれば、一つ二つ持っている方も多いと思います。
そして、賛否両論分かれるところ…
【メトロノーム】
音楽の速度を測る機器。
オランダの発明家ディートリヒ・ニコラウス・ヴィンケルが考案
ドイツの発明家ヨハン・ネポムク・メンツェルが特許を取得(1816年)
メンツェルの友人ベートーヴェンも利用したとか。
「カチコチいってるだけで耳障り」
「機械のように弾くだけ」
「人間味の無い演奏になる」
ご意見もっとも…
「テンポが安定する」
「反復練習で無理なく弾けるようになる」
「テンポ感がわかるようになる」
良い面もちゃんとあります…
私自身はメトロノームを真剣に使うようになったのは
留学中かもしれません。
難関の弾けそうにない個所を
ゆっくりのテンポから始めて
一コマずつテンポを上げていく。
指示された速度よりほんの少し早いくらいで終了。
毎日遅いテンポからはじめて
数日で弾けるようになります。
そうなれば安心。
メトロノームに頼らなくても大丈夫。
初心者さんにはぜひ、振り子式のメトロノームをお勧めします。
振り子の速度を目視することによって
速さの感覚を追いかけることができ
身体がその動きを感じることができるからです。
振り子の動きに合わせて
言葉を発してみたり
手をたたいてみたり
飛んだり跳ねたり
遊びの要素を存分に活かしてみてはいかがでしょうか。
ただし、時間を決めて
5分程度にしましょう!
メトロノームの音は案外大きいので
耳から離れなくなってしまうから!
8「楽器を構えるのも練習」
2025/01/08
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
1日練習を休むと自分にわかり
2日休むと先生にわかる
3日休むと聴衆にわかる
有名なよく知られている例えですね。
1日休むと戻すのに3日かかる、とも言われます。
本当かどうか?
それは個人差になりますが
要するに
「一度練習を休んじゃうと、ペースを戻すのが大変だよ~」
という意味です。
毎日何時間も練習するのは本当に大変です。
正直、練習を休みたいときもあります。
でも、プロは知っています。
休んだ後の戻りが遅くて自分にイライラしてしまうことを・・・
初心者さんは
本当に少しの時間で良いので
楽器に毎日触ってください。
小さいお子さんは、毎日10分でいいから
楽器ケースを開けましょう。
大人の生徒さんは、10分で良いので
楽器を構えてみましょう。
楽器を毎日構えていると
自分の身体にヴァイオリンのフォルムがフィットしてきます。
ヴァイオリンを弾く姿勢は
決して自然な形ではないので
どれだけラクに
負荷がかからないように弾くか、
ということも
大切なことだと思います。
最初に我慢して
悪い姿勢で弾き続けていくと
いつか身体が悲鳴を上げて
弾けなくなってしまいますよ。
「痛いところはないかな?」と
自分に聞いてみてください。
もし、痛いところや違和感があれば
先生に相談してくださいね。
身体の大きさ
骨格の違い
手の長さ
手の大きさ…
それぞれの最適な姿勢があります。
せっかく始めたヴァイオリン。
「なんだか痛いところが多いからやめる~」なんて言わずに
先生と相談しながら
辛抱強くしばらく続けてみましょう。
さて私も、今日の練習を始めますよ。
7「動画を使っての練習とレッスン」
2025/01/07
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
練習のお話。
大人の生徒さんは練習時間の捻出に苦労します。
ヴァイオリンっていうのは、
楽器と一緒にどれだけの時間を過ごすかによって
上達は違ってきます。
ヴァイオリンを弾くことは憧れだけど
練習していても、これで良いのか自信がない…
そんな時は、自分の練習風景を動画で撮って
先生に送信する!
私の生徒さんには動画講評形式のレッスンも承っています。
コロナ禍で激増したオンライン形式のレッスン。
ただ、相互でWi-Fi環境が整っていないと
レッスンするのは正直難しかったです
zoom機能は、元々電話会議用に設定されているため
音楽を再生するにはかなり無理があったようです。
私はそんな時、動画を送ってもらって
それに対しての講評を
テキストメッセージで返信するスタイルにしていました。
(1曲丸ごとじゃなくて、部分的に3分くらいが良いです)
更に、自分の演奏を生徒さんに送って
自主練習の役に立つようにしていました。
(二重奏の曲を先生と一緒に弾けますよ~)
☆弾けない日があっても先生の動画をみるだけでOK!
☆先生の音源と一緒に指を動かしてみる!
☆先生の音源を流しっぱなしにして聴くだけ!
大人の生徒さんだけではなく
子どものためのレッスンにも有効です。
今の時代は、工夫をすればたくさんの選択肢が選べて
勉強をする意思があれば
何でもできますね。
先生自身もどん欲に学びを深めていかなければ!と
思っています。
6「練習は弾くことだけじゃない」
2025/01/06
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
練習に関する話題は尽きませんね。
今週は練習についていろいろとお話してみましょう。
「練習は嫌い」
「子どもが練習をしてくれない」
「どうやったら練習が好きになるのか」
「効率の良い練習方法を教えてほしい」等々
プロの私でも教えてほしい内容です。
効率よく弾けるようになるのであれば・・・
苦も無くスラスラ楽譜が読めるのあれば・・・
間違いなく音程がきちんと合うのであれば・・・
凡人の私には練習しかない、とあきらめて
毎日、楽器ケースをそろそろと開けながら
ゆっくりとヴァイオリンを取りだし
弓を適切に張り
松脂をつけて
楽器を構えます。
…と、ここまでの動作、あなたは無意識にできますか?
そう、ヴァイオリンを始めたばかりの子ども(大人)は
ここまでの道のりも一苦労なのですよ。
私がピアノに憧れた一つの理由として
「ピアノのふたを開けたらすぐに弾ける」という
単純動作が好きだったことが挙げられます。
しかし、ヴァイオリンは弾けるようになるまでの状態が遠い。
乱暴に扱うと簡単に壊れてしまうので神経を使う。
私の生徒さんには
「まず楽器に慣れることを習慣にしてください」
と言って、
毎日楽器ケースを開けて
ヴァイオリンを弾ける状態になることを練習課題にしています。
そして、どんなに小さい子どもでも、
【自分で】その準備をするように伝えています。
決して親が先回りして用意しないように。
もちろん、親が横について見守ることは必須ですが
時間がかかるから、と親が手を出すことはご法度です。
それが約束できない小さなお子様のレッスンはお断りしています。
【自分で自分の楽器を準備する】
それも練習なんです!
レッスンに来るときも、楽器は自分で持ってくるように伝えます。
お母さんが大事そうに楽器ケースと楽譜カバンを抱えて
子どもが手ぶらで歩くなんて・・・NGですよ。
もちろん、人込みや電車内はお母さんが代わりに持っていても良いです。
でも、先生のお宅の前で子どもに持たせましょう。
私の母は、家を出てバスに乗るまで私に楽器を持たせ
道中は母が楽器ケースを抱えて電車に乗り
先生の玄関先で私が再び持つ、ということをさせていました。
家を出てからバス停まで、なぜ自分で持たせたか?
近所の人に「親がやらせている感」とみられないため、だったらしいです💦
私自身は「ヴァイオリンを習っている特別感」だけを頼りに
意気揚々と楽器ケースを持っていました(単なるミーハー)
今は良いですね。
肩に背負えるタイプのものが増えています。
私の時代は取っ手を持つタイプか、片方の肩に掛けるタイプのものしか無かったので
楽器ケースは本当に邪魔でした…
50代の今、軽くてスタイリッシュな楽器ケースに巡り合って
移動が楽になりました💛
関連エントリー
-
 273「5冊のノートを駆使しています」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。ノートの話・つづき。私はノートを複数使っていま
273「5冊のノートを駆使しています」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。ノートの話・つづき。私はノートを複数使っていま
-
 274「秋の気配を感じて」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる
274「秋の気配を感じて」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる
-
 275「ほんの少しの積み重ね」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある
275「ほんの少しの積み重ね」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある
-
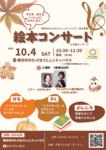 276「心に届く演奏を」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。
276「心に届く演奏を」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。
-
 277「絵本コンサート・終了と反省①」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子
277「絵本コンサート・終了と反省①」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子