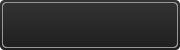- ホーム
- ブログ
ブログ

66「練習後の身体メンテナンスも大事です」
2025/03/07
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

今週は初夏のような暖かさだったり
真冬のような雪の日があったり
心身ともに
アタフタしてしまいました。
ヴァイオリンを練習するにも
準備運動が必要です。
深呼吸をしたり
ゆっくりと腕を上下に動かしたり
肩甲骨から腰までを
充分に伸ばしてから始めないと
弾いている途中で
腰や肩が痛くなります。
(練習意欲が激減します・・・)
練習が終わった後も
丸まった肩や
緊張した左腕を
ゆっくりと伸ばしてあげないと
身体がギクシャクします。
50代は、自分自身で自分をメンテナンスすることが
とても大切だと思います。
3年前に五十肩症状で整形外科に通っていたころ
「ヴァイオリンの練習が終わってからも、
ちゃんと肩を動かして元に戻してくださいね」と言われました。
「元に戻す!」
練習前の準備運動だけを考えていた私には
とても新鮮な響きでした。
練習時間が立て込んでくると
気持ちに余裕が無くなって
自分の身体を疎かにしがちです。
集中して練習に対して良い時間が過ごせることも大切ですが
自分の身体をメンテナンスすることも
同じように大切なことだと改めて思う金曜日。

練習が終わったら何を食べようかしら?
という
ワクワクした気持ちも
大切だと力説したい。
65「動画で講評」
2025/03/06
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
先日、次女から
「演奏動画を見て講評してほしい」と言われました。
近頃の音楽講習会やコンクールのプレセレクション(予選)、
果ては音大の入試にまで、動画審査が組み込まれることが多くなりました。
自分で演奏したものをYouTubeにアップし、書類をPDFで事務局に送信する。
または、申請時に自分専用のポータルサイトが割り当てられて
そこに提出物を格納してく方法など・・・
コロナ禍をきっかけにデジタル化が進みましたが
音楽世界も今や常識として、当たり前のように変化しています。
少し時代に乗り遅れている私には、ハードルが高いと感じられることですが
若者たちは果敢に挑戦しつつ、それらのことをスタンダードだと思っているようです。
私の学生時代も音源審査というものは存在していました。
その頃は、高性能マイクを借りてきて
自宅のリビングなどで録音して
そのまま郵送するという方法しかありませんでした。
ドイツ留学時代には、「レコーディング技師専門課程」のような学生にお願いして
音大のホールを使って録音してもらったこともありました。
その当時は録音だけなので、音響だけを考えれば良かったと言えるでしょう。
たとえ汗だくでTシャツと短パンで弾いていても、音源がよければOK。
しかし今の時代は動画。
録音の音響はもちろんのこと、録音場所、服装、姿勢、楽器の見せ方なども
考えなくてはなりません。
次女は何度も動画は作成しているので慣れたものです。
少ない選択肢ながら録音場所を確保して、何回か録音したようです。
何度も録音していると、客観的に自分を見るのは難しいことは確かですね。
3つの動画をみて、どう思うのか意見が欲しいとのこと。
最終決定は自分で決断してね、という条件で講評を引き受けました。
演奏を聞いて講評するのは結構大変です。
私の場合は次の3つを講評します。
- 始めの3分でファーストインプレッションを判断
- 全体の流れを聞いて音楽的な構成力と表現力を判断
- 上記を聞きながら気になったマイナスポイントをチェック
*マイナスポイントをチェックというのは
技術的な改善点を指摘するということなので
時に厳しく、時に大きな課題として提案するといった
幅の大きいものになります。
1回の再生で、このポイントをすべて網羅してメモします。
何度も聴きません。
次女とは、聞き終わった後にfacetimeで私の意見を伝えました。
生徒さんの場合には
メモを見返しながら
- 現状の客観的な確認
- 改善するための練習方法
- 次までの課題をお伝えします。
この返信が結構時間がかかるのですが、自分の勉強にもなっています。
さて、次女がどの動画に決定したのか?
最終決定は自己判断なのでわかりませんが
そもそも動画を作成するということは
相当練習しないと出来上がらないので
2月の初めに送ってきた動画よりも
月末に送られてきた動画の方が
はるかに完成度が高かったのは事実でした。
頑張れ!
若者!
64「五感を磨く」
2025/03/05
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
今日は啓蟄(けいちつ)。
啓はひらく。
蟄は土の中に閉じこもっていた虫、という意味。
春の息吹を感じて冬ごもりから虫たちが目覚める、
といったことでしょうか。
私は公式LINEで
二十四節気に沿って
四季の移り変わりを意識するメッセージを配信しています。
ゆるやかに季節を感じ
今、自分に必要な大事なことを
ゆっくり思い返してもらう・・・
そんなゆるやかな配信ですが
読者の方から
「今日はゆっくり休みます」
「私もそのお菓子を買いに行きます!」なんて
ポツンとメッセージをいただいて
ほんわかとしたやり取りを楽しんでいます。
(登録人数現在11名ですが・・・)
なぜ、音楽家なのに二十四節気??
二十四節気は古代中国の黄河流域の気候をもとに
つくられたとのこと。
日本の季節感と少しズレることがありますが
今なお言い伝えられ、生活に組み込まれるのは
積み上げてきた文化と思考が
この二十四節気を必要だと感じているからでしょう。
私は日本の四季を美しいと思っています。
そして、その四季を愛おしく大切にしながら
生活の中に取り込んでいる日本人を
とても誇りに思っています。
行事やしきたりの一つ一つに意味があり
ずっと続く伝統の中に
しっかりとした芯があり
自然と共に歩んできた試行錯誤が見え隠れします。
2月の寒さも
3月になって同じような気温だとしても
「ほんの少し空気がゆるむ」
「陽ざしにほんのり明るさが加わる」
といったように
微妙で繊細な変化を読み取る感性が
日本人には備わっているように思います。
田畑で作業する人たちの
土の感触から何を植えるべきか
何を加えるべきか
もしくは何を排除すべきかの判断を
肌感覚で感じる五感の鋭さを
私たち一般人も
「なんとなく」理解しているように思います。
西洋人には敵わない
日本人だからこそ感じられる繊細さを
音楽家としてこれからも
存分に表現していきたいものです。
せっかく日本人に生まれたのですから。
二十四節気を意識すると
その時期によっての食べ物の息吹や
身体が欲している食材
弱っている部分を改めて感じることになり
「人間ってよくできている」と
感心することになります。
音楽家は身体が資本。
波があるのは当然ですが
「良い塩梅」を探して
生きていくことができれば
「音楽を届ける」仕事も
ちゃんとできるのではないか・・・と
思っています。
結局、私は食べることが好き、という
結論になっているような気がする・・・
63「演奏するということ」
2025/03/04
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
少しずつリハーサルが本格化してきました。
自分の練習が、指を動かす内向きなリハビリ期間を経て
【演奏する】という総合的な
外向きへの準備が開始された感じというのでしょうか。
プログラム構成を考えた時と
お客様へ向かって演奏するときの誤差がないように
じっくりと、
丁寧に作り込んでいく過程です。
コンサートで何を伝えたいのか?
曲間のMCでどのようにプログラムをつなげていくのか?
お客様の気持ちの変化を予想したり
ワクワクする時間
落ち着く時間
取り交ぜながら
どのようにガイドしていくのかをじっくり計算しています。
忘れてはならないことは
どんなことがあっても必ず
【本物】を届けること。
私の信念です。
リハーサル時に
ピアニストとの話でヒントを得ることもあります。
予想していたタイミングとは
全く違う間合いでみつけた正解のかけら
ふとひらめいた面白いエピソード
ピンときた斬新なアイデア
リハーサルだからこその
五感をフル活用した
音のおしゃべりは
私が一番生き生きする時間かもしれません。
そう、こんなところに
私の【好き】が眠っているのかも。
音楽を聴きながら
楽しそうにしている子どもたちや大人のお客様。
私にとって
コンサートでたくさんの笑顔に出会えることが
練習やリハーサルの先に見える
自分の使命なのだと
改めて思います。
62「3月がくると思い出すこと」
2025/03/03
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

3月になると気が引き締まります。
14年前の東日本大震災へ思いを寄せることになるからです。
私はあの頃、子育て真っ最中でした。
長女が小学校4年生。
次女が幼稚園を卒園するタイミングでした。
押し寄せる情報に翻弄されながら
自分の生活を守ることに必死でした。
混乱した世の中で
「音楽家として何か支援をしたい」
という音楽界の動きも活発でした。
実際に被災地へ行って
音楽を届けたり
楽器を届ける活動をする音楽家がいました。
自分自身が動けずに
「なにもできることがない」
「音楽なんて喜ばれないのではないか」と
嘆く音楽家もたくさんいました。
私自身は
何もできないことを自覚し
自分のことを優先していたので
音楽家としてできることはなく
それでも、3月末に仲間のピアニストから
「チャリティーコンサートをしたいので
一緒に演奏してほしい」と言われて
その年の7月に演奏したことが
とても嬉しかったことを覚えています。
そのチャリティーコンサートは
今も続いていて
頻度は減ったものの
コンサートで弾くたびに
あの時のことを思い出すことになります。
私が音楽家として支援できることは
本当に些細なことしかありません。
忘れないこと。
毎年3月に思い出すこと。
それしかないのです。
今年の3月は
演奏する機会をいただいたので
14年前を忘れないような
プログラムを組み、心を込めて演奏します。

関連エントリー
-
 273「5冊のノートを駆使しています」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。ノートの話・つづき。私はノートを複数使っていま
273「5冊のノートを駆使しています」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。ノートの話・つづき。私はノートを複数使っていま
-
 274「秋の気配を感じて」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる
274「秋の気配を感じて」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる
-
 275「ほんの少しの積み重ね」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある
275「ほんの少しの積み重ね」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある
-
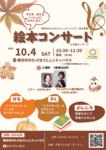 276「心に届く演奏を」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。
276「心に届く演奏を」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。
-
 277「絵本コンサート・終了と反省①」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子
277「絵本コンサート・終了と反省①」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子